おはこんばんちわなら
さて、去る2024年6月7日~9日に、第69回日本透析医学会学術集会・総会が開催されました。
今回はその回顧録?を書いてみたいと思います。
いや~このブログ、読んでますよ!!という方々にも出会うことが出来たのはとても有意義かつ励みになる事でした。ありがとうございます。
さてさて、何書こうかな~。と思いながら筆を進めます。
Day1
Year in Review
Year in Reviewから始まった今年の学会。この1年間の注目すべき論文紹介が行われました。筆者は途中参加でCKD-MBD辺りから参戦。CKD-MBDは筆者も好きな分野なので、結構真剣に聴講しました。
新ガイドライン改訂に向けた動きが活発になる中、その根拠となる論文の紹介やこれまでカーブを描いてHRが上がるP,Ca,PTHに関しても、新機軸となる時間依存性HRの解説がありました。やはりどのパラメーターも高値はリスクであるという点には注目ですね。
他にも、PDはHDと比較して主要心血管イベントが有意に低いという報告や、PD関連感染症を除く感染症であれば、これもHDと比較して低いという報告の紹介がありました。結構PDって優秀ですね。筆者は携わったことが無いので、実感が無いです。
テナパノル塩酸塩(フォゼベル®)についての報告もありましたが、こちらは正直治験時のデータの紹介に留まるのみで、目新しい情報はありませんでした。ただ、薬剤としては優秀の一点です(あ、フォゼベルについても記事にしているので、よければ御参照下さい)。
フレイル・サルコペニア
他のsessionでは、フレイル・サルコペニアやPEWに関して聴講しました。
フレイル・サルコペニアに関して、疑似運動薬なんてことを考えている事には驚きましたね。その手があったか~って感じです。そしてフレイル・サルコペニアがなぜ注目されるのか、対策をしなければならないのかについて、毎度おなじみな感じで解説がありました。運動が骨代謝バランスを整える旨の報告や、最近ではよく見聞きする鬱に対する効果なども解説がありました。運動ってホント大切ですね。
あ、フレイル・サルコペニア・PEWについても記事を書いてますので、良ければご覧ください。
まぁ筆者はチェリーピッキングが好きなので、聴講した内容もCKD-MBD sessionが多いこと。
で、CKD-MBDによる骨代謝と骨格筋の関係によるフレイル・サルコペニアの重要性という側面がよく語られていましたね。リン負荷は骨格筋を障害する。や骨格筋量が少ない患者は骨折のリスクが高い事(海綿骨と皮質骨のお話はここに繋がります)。FGF-23は炎症/酸化ストレスを介して骨格筋の萎縮を招く。等など。
PTxは術後に骨格筋量を増加させる。というのはなるほどそうか。と考えさせられましたね。今じゃ技術の継承に難渋しているとか。
あとは、nPCRと骨折の関係ですかね。これの低下は骨折に関連するので、nPCRの落ちない食事を提供する事が大切だとありました。
日本の透析患者の骨折の特性という話題では、日本は諸外国に比べると骨折のリスクは低いということでした。これはPTHの管理目標が諸外国にくらべ低く設定されているからでは?という話です。そして、iPTHとALPが低い事は、骨折のリスクを下げることもDOPPSの解析から判明しています。やはり管理目標を達成することは大切ですね。
Day2
聴講したsessionの中で、HI-HDFについてという演題がありました。高頻度頻回間歇補液血絵透析濾過というものです。
ただこの弱点、補液のたびに血流量が落ちるので、Kt/Vがかなり落ちる。という話でした。ん~良し悪しですね。循環動態の維持はいいですが、老廃物の除去が出来ないのでは、透析をしている意義が薄れてしまいます。バランスって難しい。
HIF-PHiの講演も聴講しました。
鉄欠乏は血栓症のリスクとなるということで、鉄補充の重要性が語られていましたね。これは、HIF-PHiが鉄の利用障害を是正するため、貯蔵鉄が利用され、結果として鉄欠乏を引き起こす。という機序です。Hepcidin-25の発現は鉄を囲い込む方向へ働きます。それを不活化することで、鉄の利用障害を是正するのが本機序です(簡単に言ったなおい)。
あ、Hepcidin-25や鉄欠乏性貧血に関しては別記事を参照してください。
で、ちょっと驚いたのがHIF-PHiと悪性腫瘍のお話。従来なら悪性腫瘍のある患者にHIF-PHiってまぁ禁忌だったと思うんです。ただ、実験で出た可能性が、HIF-PHiが貧血を改善することで、悪性腫瘍による血管新生が促がされ、結果として抗がん剤が届きやすくなり、奏功する可能性がある。という報告でした。目から鱗でしたね。ちゃんとした結果が欲しい所です。
保存期腎不全における血清鉄代謝マーカーおよび鉄剤と心血管疾患との関連
後々書きますが、心腎鉄連関に関するお話でした。
保存期CKDの患者でも、TSAT>20%以上の維持が、低いCVD発症のリスクと関連していた。という話題です。
TSAT<15%の患者は死亡率やMACE:Major Adverse Cardiovascular Events(主要心血管イベント)の発症に寄与するということで、透析導入前から鉄欠乏性貧血の管理は重要だという事が良く分かります。これらはCKD-JAK Studyによるコホート研究の結果です。
実態調査から考えるCKD治療の課題~腎性貧血の治療意義をまじえて~
CKDと心不全:HFは隣り合わせな疾患ですが、やはりHFの管理ということで、BNP測定は重要である。というお話でした。
市中では様々な薬剤が患者に対して処方される訳ですが、実態調査としてアンケートがとられており、ARNI(エンレスト®)に対して何を期待するか?というアンケートには、蛋白尿の抑制やCKD進展予防が大きく期待される効果として注目されていました。さすがはエンレストですね。
ただ、エンレストが出される患者はBNPの測定が正確には出ないため、NT-pro BNPでの測定が必要です。その点に注意しましょう。
Day3
透析患者の栄養障害と貧血管理~健康寿命を延伸するために~
Day2で述べた心腎鉄連関:Cardio-Renal-Fe Syndrome(CRFeS)についての話題。従来は心不全ー慢性腎臓病ー貧血連関:Cardio-Renal-Anemia Syndrome(CRAS)の概念が提唱されていましたが、最近は貧血でも鉄欠乏性貧血にフォーカスが当てられるようになり、新たな概念が提唱されつつあるようです。
我が国の保存期CKDの現状
高血圧症の患者数は潜在数も含めると4,300万人、糖尿病患者数は1,200万人、そして糖尿病患者はFANTASTIC4の登場により高齢化が進みます。
ではCKD患者の数はどうなのか?→2015年の推計で1,480万人に上ります。
しかし、CKDの6割は未診断であるという調査結果があります。ではなぜ診断に行きつかないのでしょうか。その理由としては下記が上がります。
- 早期stageでは特異的な症状はない
- 認識が無い
- 尿検査が十分に活用されていない
- 実臨床では疾患認識および優先順位が低い
これらが相まって、診断率は低迷しています。普及活動って大切ですね。
さて、ほんの数年前まで導入原疾患1位だった糖尿病性腎症:DKDですが、ではなぜ日本人やアジア人は透析導入に至りやすいのでしょうか。それは人種間の差異によるものです。アジア人はインスリン分泌が少ないため、ダメージを負いやすいと。そしてこの人種差の更に突っ込んだ話はなにかというと、教科書ではこれまで「ネフロンは100万個ある」というものでしたが、実は日本人では66万個程度しかないことが分かっています。これが導入にいたるからくりということです。
また、近年では薬剤の進歩が凄まじく、SGLT2阻害薬は特に優秀です。
CREDENCE StudyというeGFR低下を比較した試験があります。
この試験では、4年間に渡りプラセボ群とSGLT2阻害薬群のeGFR低下スピードを比較しています。幸いにして試験中に透析導入になったわけではありませんでした。結果としてSGLT2阻害薬群の方が、プラセボ群と比較して低下スピードを緩徐にするという事が判明しました。
しかしここで疑問が発生します。では具体的に、いつeGFRが10を切り、透析導入となるのか?でした。
そしてこの試験のシミュレーション結果が公開された時、中々衝撃が走りました。
プラセボ群はそのままでは約十年後にeGFRが10を切るというシミュレーション結果に対し、SGLT2阻害薬群のシミュレーション結果はというと、プラセボ群から更に6年ほど腎機能を保護する結果となりました。透析導入を6年遅らせることが出来るようになったわけです。これは医療経済的にもとてもインパクトのある結果となりました。
eGFRの低下スピードを緩徐にする施策というのは他にもあるようで、例えば患者だけの努力ではなく、そこにメディカルスタッフが介入する事でも、低下スピードを緩徐にすることが可能なようで、その為今回の診療報酬でも新たに看護師・理学療法士の介入に報酬が付いたわけです。
とまぁ、CKDの話題はここらへんでしょうか。
貧血やフレイルのsessionも聴講しました。
当たり前ですが、フレイルの患者は入院・死亡率は上昇するようです。ではフレイルを予防するためにはどうすればいいか?それはタンパクの摂取です。で、問題となるのが透析による細胞飢餓。透析中はどうしてもアミノ酸やインスリンの漏出により、エネルギーが枯渇します。その為、蛋白異化亢進を促す為にも、透析日は透析中に食事をすることが推奨される。というお話でした。
貧血については、Hbサイクリングを抑制することも大切ですが、Hepcidin-25の活性を抑制するという意味でも、CRP>5.0mg/L以上の患者にHIF-PHiが有効ではないか?というKDIGOのガイドラインが出ているようです。これは要チェックしたいところですね(難易度高いですけど)。
透析患者の栄養障害と貧血管理
MIA症候群(PEW)と透析というのは切っても切れません。
そしてもう一つにCKD-MBDという概念もあります。これはROD:腎性骨異栄養症と昔言われたもので、それが拡張して血管石灰化などに進展したものです。
ここにPTHは欠かせない訳ですが、PTHが高い患者というのは低栄養の可能性があるというのです。
そして野菜や果物を多く摂取している患者では予後がいいという事が分かっています。その為、カリウムがさほど上がらない患者に関しては、積極的な摂取が推奨されるとありました。バランスって大事ですね(小並感)。ヨーロッパのガイドラインでは、カリウムが常時6.0mEq/Lを超えない患者に、高カリウム血症治療は必要ない。とまでステートメントが出ています。しっかりと参考にしたいところですね。
さて、これに続いてテナパノル塩酸塩(フォゼベル®)のお話もありました。ただこの話はエビデンスは薄弱ですね。機序としてはそうなんでしょうけど。
テナパノル塩酸塩は本来はリン吸収阻害薬として使われます。副作用にはどうしても下痢が存在します。しかし、この下痢を逆手に取るのです。
ESRD患者というのは、カリウムとリンの排泄経路にメインとして腸管を使います。しかし、便秘が起こることで、これら老廃物が排泄されず、結果として高カリウム血症が発症する。という機序です。であれば、下痢で腸管を常に動かし、老廃物をしっかり出してしまおう。というストラテジーです。
テナパノル塩酸塩の治験で高カリウム血症に対して効果があったという説明はありませんが、阿部先生の言っている事にも一理あるので、誰か検証して欲しいところですね。
さて、栄養障害に関して、では透析患者は1日にどれだけ運動をすればいいのか?というお話です。
よく言われるのが、健常人で1日8,000歩以上という話ですが、透析患者に関しては最低4,000歩という話で、フレイルを来たしている患者は5,000歩。ノンフレイルでも5,000~7,000歩は必要という事でした。
咀嚼機能の低下から糖尿病、オーラルフレイル→全身フレイルへと進行する恐れがあること。この逆も然りという事でしたので、食欲や嚥下機能などは注意が必要かもしれません。歯の欠損はそれだけで過食・偏食傾向にもなるので、管理が重要です。
展示ブース
展示ブースも、そんなに大きな広告はありませんでしたが、東レと日機装では、新商品の発表があったので、少しお知らせします。
HVSIモニタ
この子は6月に入り販売が開始したばかりのデバイスになります。手のひらサイズで可愛らしいですが、シャント狭窄などを専用で計測するデバイスで、とてもいい相関が取れると好評なようです。

東レ新製品群
今回、大手メーカーで唯一新製品が発表されたのは東レメディカルです。
姿はTR-10EXですがそれを踏襲した個人機「TR-20EX」が発売されます。

そしてTRシリーズに新たに?追加されたのがICカードリーダー機能です。
愁訴処置などで、一々実施者の名前を入れなくても、カードをピッとしたら名前が入るようになります。地味に工数が減る機能なので、まぁ便利なのではないでしょうか。
そしてBMSー所謂BV計ですが、これもマイナーチェンジが加えられています。


ブログの構成上、縦長で申し訳ないですが、上の写真が旧BMS、下が新BMSです。一々測定のためにパーツを追加する必要が無くなったのが一つと、さらに小型・軽量化されたため携帯性は向上しています。
但し、日機装やJMSをお使いの方であればお分かりかもしれませんが、この子、単品では再循環率は測定できません。手動で希釈法をしなければならない。という欠点があります。再循環など、VA管理に使いたい人はこの点で他のメーカーに分があるかもしれませんね。
筆者はBV計は血圧管理や純粋にBV測定に使いたい事や、別に再循環には使わなくてもと思っているので、そこは気にしませんね。
また、新製品群に東レ透析部門システムの「MIRACLE DIMCS UX」から更に進化した「MIRACLE DIMCS EX」が登場。Full HD対応になり、1画面で作業が済むようになりました。
体重測定時にも検査やX-pの有無が分かるようになり、撮影忘れなどのインシデント軽減につながる設計がされています。
あとがき
さて、今回は筆者初のパシフィコ横浜参戦となりました。
このブログを見てくれている方にもお会いでき、励ましの言葉も頂けたので、それだけでも十分収穫かもしれません。
筆者とエンカウントして頂いた著名なアカウントの方々にこの場を借りてお礼申し上げます。
てなわけで、学会レポ回はこれにて終了。
ブログネタは随時受付中!!ではまた~




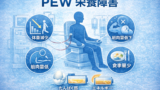





コメント